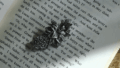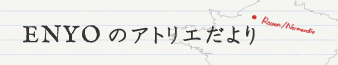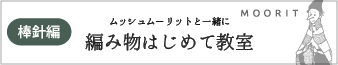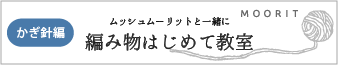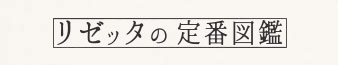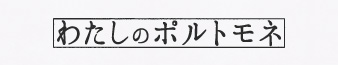イベント・ニュースや読みもの note
23.07.31

《つくり手ファイル》インドの手仕事にわたしたちらしさを重ねて/BUNON吉田謙一郎さん、浅野愛美さん
インドならではの特別な手仕事と、毎日着たくなるような都会的な雰囲気。その2つが共存するBUNONの服づくりのはじまりは、なんと森で蚕を探すところから。気の遠くなるような時間と手間をかけて、洋服は私たちのもとにやってきます。
そんなものづくりの背景を、ディレクターの吉田謙一郎さん、デザイナーの浅野愛美さんにお話をうかがいました。
■自然の恵み、人の手を経て生まれるぬくもりある洋服
初夏の日差しが心地よい6月の終わり。住宅街にひっそりとたたずむBUNONのプレスルームにお邪魔しました。


2019年から始まった、ファッションブランドBUNON。吉田さんと浅野さんのお2人を中心にデザイン・運営を行い、お洋服はすべてインドにて生地から生産されています。
建築家の方がつくられたという個性的なタイルが印象的な空間には、それぞれ時間と手間をかけてつくられたBUNON の洋服が並んでいました。


豊かな色彩を巧みに取り入れながらも、手仕事でつくられた生地はどこか落ち着いた印象です。ずらりと並ぶと、どれもそれぞれの色をまとってなんだか楽しそうに調和していました。

BUNONはシルクを使ったアイテムも多いですが、間近で見ると同じシルクの生地とはいえ、印象はさまざま。
「このシルクは、繭から蚕が自然に出るのを待ってから紡いでいるんですよ」と見せてもらった生地は、わたしたちが思っていたシルクとは違った質感で、より自然な印象も。

吉田さん:「シルクは天然のもの。私たちのインドのパートナーは森に蚕を取りに行って、シルクをつくっています。いつもいる場所に蚕がいないときもあるし、とれる時期によって風合いが違うこともあります。
天然のものなので当たり前ですが、同じ生地をつくって欲しい、というときでも100%同じにはならないんですよ」
浅野さん:「その蚕から糸を出して女性が太ももで糸を撚り、それを男性が織機で織ります。
糸は太ももを使って撚るので、男性に比べ太ももが柔らかい女性にしかできません。その部分は男女で分業されているんです」

「手紡ぎ・手織り」その言葉をつくりあげるには、本当に多くの時間と人の手がかかります。さらに、そこにプリントや刺繍、手仕事を施しBUNONの洋服は完成していきます。
■ある布に魅了されて
BUNONを始めたのは2019年。きっかけになったのは、ある一つの布との出合いだったそう。それは今ではBUNONの定番となったシリーズに使われている、ほどよい光沢のある手紡ぎ・手織りのシルク生地です。

吉田さん:「インドのパートナーとなるスミトラさん・スリマさん夫妻との出会いは、パリの展示会でのことでした。その後、彼らがつくっている生地を日本に送ってくれました。
このような生地を今でもつくっているところがあるんだ、と一番最初はそれが驚きで。この生地を使って何をつくろう、とわくわくしたのが始まりでした」

「あとでわかったことなのですが、インド国内でも伝統的な手紡ぎで布をつくっているところは本当に少ないんです。また海外の展示会では、このように声をかけてくれる方は意外と多いのですが、繋がっていくことは少なくて。
いろいろな縁とタイミングが重なり、こうして繋がってこれたことを本当に嬉しく思っています」

■関係を築きながら一歩ずつ。今では家族のような存在に
そうして始まったインドとの新しい関係ですが、最初は驚きや試行錯誤の連続だったといいます。
吉田さん:「やはり文化や考え方が違うので、最初は意思の疎通に苦労しました。
日本人はこうお願いしたらこれと同じもの、もしくはこれに近いものが届くと思っていますが、向こうは違うんですよね。あるときは依頼とはほど遠いものが届いたこともありました(笑)」

そんなときに役立ったのは、やはり直接のコミュニケーションだったそう。
吉田さん:「コロナ以前には、3回ほどインドに直接行って話すことができました。直接話すと、スミトラさん夫妻と好きなものが似ていたり、年齢が近かったりもあって、すごく距離を縮めることができたんです」

「根気よく説明をして、それを繰りかえす。そうすると徐々に『これはどうしたらいいの?』と聞いてくれるようになり、サンプルをつくる前に想いの共有ができる。
5年間試行錯誤しながら、お互いを尊重する関係をつくることができたので、最近は本当にスムーズにいくようになりました」
浅野さん:「インドでは、『ファミリー』という感覚がとても強いんです。わたしたちはファミリーだから、なにかあったら言って欲しいと。
けんかすることもあるけれど、それはファミリーだから、としきりに言ってくれます。最近はスミトラさん夫妻とお子さんが日本に来てくれて、一緒に富士山を見に行ったりしました」
■インドのよさと、自分たちの「着たい」のバランスを丁寧に考えて
ぱっと見ただけではインドでつくっているとは感じさせないような、都会的な雰囲気がBUNONの服にはあります。日本のデザインとインドの手仕事が絶妙なバランスで掛け合わされているので、普段着に着たいけれど特別。そんな他にはない存在感が生まれる背景をうかがいました。

浅野さん:「インドの手仕事は素晴らしいけれど、自分たちがつくるなら民芸品のような雰囲気にはしたくなくて。もちろんそういったものもとても素敵なのですが、自分たちがやるのであれば、温かみもありながら洗練された、毎日のコーディネートがイメージできるようなものづくりがしたかったんです」
吉田さん:「そこにインドならではの手仕事が入って、新たなものが生まれるような感覚です。お互いがプラスになるよう、バランスは大切にしていますね」

BUNONの洋服は、わくわくするような柄や色合いが印象的でもありますが、そのときどきで印象的だったものや事柄からインスピレーションを受け、柄や色を決めているそう。
浅野さん:「2023AWのテーマは『夜の虹』なのですが、このテーマはある写真から生まれました。去年3年ぶりにNYの展示会に出展し、その搬入後の写真にたまたま虹が写っていて、とてもよい予感がしました。その瞬間、「次のテーマは絶対虹にしよう」と心に決めました。
虹をキーワードに考えるなかで実際に夜の虹というのがある、ということを知り、BUNONとしての7色を決めました。
全体を見ながら色のバランスは二人で考えて決めて行きます。夜というテーマをもとにモノトーンのものを増やしたり。二人のもともとの好きなものも似ているので、すんなりと決まっていきますね」

「日々の生活の中で出合う美しい瞬間や耳に残ったことばなど、柄のインスピレーションはいろいろなところから生まれています」
■あえてインドでつくる、を大切に
もともとの出合いは一枚の布。インドのパートナーであるスミトラさん夫妻はもともと生地屋さんで、インド国内でサリーのブランドはしていたが洋服をつくったりなどはしていなかったそう。
吉田さん:「生地だけを仕入れて、ということも考えました。でも、実際にはここまでの手の込んだものづくりは日本でも難しいことなんです」
浅野さん:「日本のパターンナーさんに見せても驚かれるような仕事なので、日本でつくろうと思うと逆に難しく、インドだからこそできるものかもしれません」

吉田さん:「森に蚕を取りにいって、その糸を太ももをつかって紡ぎ、織る。さらに刺繍を一点一点施す。
自分たちがやろうと思っても到底できないような、途方もない時間のかかる仕事ですが、彼らはそういった手仕事には効率を求めていないんです。
文化の違いがあるからこそ、僕らの想像を超えたコレクションができたり、私たち日本人を含めた世界の人たちにとって特別な印象をもたらすものづくりが生まれるんですよね」

「また、生地の仕入れでは限定的な仕事になってしまい、この貴重な伝統を残してはいけません。手仕事を後世に残し繋いでいくためにも、インドでつくるということに重きを置いています。
刺繍ができる人が減ってきていたり、インドの中で手工芸の失われる危機は常に感じているので、そこをどうやってきちんと仕事として成り立つようにできるか、を考えています。

ものづくりを一緒に楽しんでくれるパートナーと出会い、つくりたいものを協力しながらつくっていくことができているので、インドの手仕事を守っていくためにも継続させていくことが一番大切だと思っています」
写真提供:BUNON(7、10、12、18枚目)
-

《つくり手ファイル》人生に寄り添うジュエリーづくり/cobaco
-

《つくり手ファイル》横振り刺繍が紡ぐ、野の花のジュエリー/鬼塚友紀さん
-

《つくり手ファイル》使う人とのほどよい距離感/JOURNEY草薙亮さん
-

《つくり手ファイル》日本の豚革を活用、未来につながるものづくり/sonor
-

人生に向き合う中で、見つけたセルフケア。「自分の内側が何を望んでいるのか、ひとつずつ向き合う」/fragrance yes 山野辺喜子さん
-

《つくり手ファイル》五感に響く、木の装身具/KÄSI 渥美香奈子さん