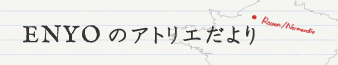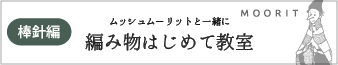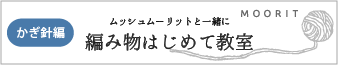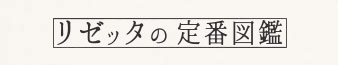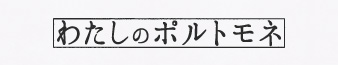イベント・ニュースや読みもの note
2020.04.13

《つくり手ファイル》器に光を映すように/陶藝家・瀬川辰馬さん
まるで古代の出土品のような、静かな詩情を湛えた器をつくる瀬川辰馬さん。どのような思いで器づくりに取り組んでいるのか、オンラインショップでの個展に先がけ、お話を伺いました。

■素材と手があれば生み出せる
陶藝家・瀬川辰馬さんによる、土の中で眠っていたかのような自然な風合いの器。
ひび化粧と銀彩をほどこしたその表情は、空気に触れ、使っていくことで少しずつ落ち着いたものへと変化していきます。


瀬川さんは1988年生まれ。大学でメディアアートを専攻していましたが、その卒業制作展が東日本大震災により中止になったことが、作陶の道に進むきっかけになりました。

「電力があって、wi-fiが飛んでいて、OSのバージョンが最新で…。 メディアアートは、無数のインフラがあったうえでようやく実現するものです。
震災やそれに伴う計画停電を通じて、いかにそれが微妙なバランスの上に成り立っている表現形式なのかを実感させられて。対照的に、素材と手さえあればつくることが出来てしまう、工芸の地に足のついた強さに憧れを抱きはじめました」

そうして大学院への進学をやめ、多治見市の陶磁器意匠研究所 へ。二年間陶芸を学んだのちすぐに東京・北千住でアトリエを開き、自らの制作活動をはじめました。

■器に光を映すように
「僕はもともと工芸畑の出身ではないので、良くも悪くも器や陶芸という言葉についてオーセンティックな定義が自分のなかにありません。
そこに含まれるイメージの広がりをいちいち自分なりに解釈しながらつくっているようなところがあります」

「つくっているのは器という生活の道具ですが、それを通じてもっと抽象的ななにかについて考えを巡らせようとしているのかもしれません」

「形のない光そのものを追い求めるような生き方は、人をあまり幸福にしないと思っていて。
そういう光がきれいに映り込めるように、質量の伴ったなにかを具体的に磨いていくほうが生産的だと思うし、それって生者だけに許された数少ない特権だとも思うんです。
僕にとっては、たまたまそれが器づくりなんです」

■生と死の循環を抱きとめる器
「器というかたちにこだわって仕事をしているのは、"生と死"という普遍的で汲み尽くせないテーマがそこに含まれているように感じるからです」
そう軽やかに、瑞々しく話す瀬川さんの背景にあるのは、自身の死生観でした。

高村幸太郎著『智恵子抄』に、亡くなった妻・智恵子を想ったこんな一節があります。
『(亡くなった)智恵子はすでに元素にかへつた。わたくしは心霊独存の理を信じない。智恵子はしかも実存する。…』
智恵子を形づくっていた元素は今も私と共にある。この詩をはじめて読んだとき、瀬川さんは救われたような思いがしたといいます。

「人にはいつか必ず死が訪れるということに対して、どう納得していけばいいんだろう…と、無宗教の自分なりに“死”というものに対して考えを巡らせていったときに、この“物理的な循環”の物語に共感するところがあったんです」

「かたちあるものはすべて元素でできている。地球にある元素の数自体は大きく変わっていなくて、長い時間をかけて、姿を変えながら循環していっています。
陶芸という技術自体、鉱物が砕けて堆積したものを、再び焼きかためるというある種の流転を取り扱うものですし、そうして焼き上げられた器という道具自体も、生と死の循環を抱きとめることが根本的な機能だと思っています」

「食べ物も花も、生きたまま器に載せることはできないですよね。
少し言葉としては強いかもしれませんが、そういう意味で器はある種の棺だと思うんです。人は日に三度それを握って生きている。
食事の時間は人間にとって純粋な生活の楽しみであるのと同時に、自分がある循環のなかで生きているということを実感する祭事としての側面もあると感じています。
僕は器という道具を、そういうかたちで生と死が循環していくのための祭器、というつもりでつくっています」

■自分なりの物語をそこに綴っていくように
瀬川さんが近年つくりはじめたという銀彩のシリーズは、リムのない皿や鉢、四角い箱など、フォルムがすっきりした器ばかり。
何を載せるか、どれくらい入れるか、使う人にゆだねるような印象があります。


そして、色も形も同じものはひとつとしてありません。
「ひびの具合や、色のグラデーションなど、厳密なコントロールはできません。
ある理想があって、そこからどれだけ外れてしまったかという減点方式の制作というよりは、思ってもなかったような表情が出た、という加点方式の制作と言えるかもしれません」

「器というかたちの潔いところは、中が"からっぽ"なところだと感じています。
つくりながら僕自身が考えていることを今日は色々とお話しましたが、成果物としてできあがった器の中心部は結局のところ空白。
その空白を何で満たすのかは使う人なりのイマジネーションがあるだろうし、そうしてはじまる、器それぞれの物語を肯定したいなと思います 」


食事を載せたり、小物を置いたり。何も入れずに飾るというのもひとつの使い方です。
瀬川さんから受け取った、豊かな余白をそなえた器たち。自分なりの物語をそこに綴っていくように、器の空の部分を思い思いに満たしていってほしいと思います。
■オンライン個展を期間限定開催
二子玉川shedにて展示を行う予定でしたが、外出自粛を受け、皆様の安心と安全を第一に考えて、店舗での開催は中止します。
代わりに、オンラインショップ上にて、一部作品の期間限定販売が決定!遠方の方にも瀬川さんの器を見てもらえることになりました。

食事の時間がいつもより大切に感じる今日に、 瀬川さんのつくる「祈り」のような器を取り入れて、家で過ごすときを楽しむのはいかがでしょうか。
オンライン個展は4月16日(木)12:00から開始予定です。