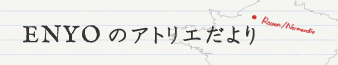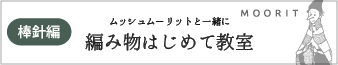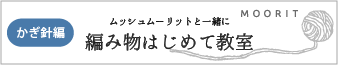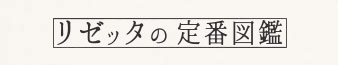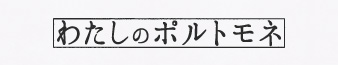イベント・ニュースや読みもの note
2021.06.15

《つくり手ファイル》素材そのものの美しさを引き出す、かごづくり 宮本工芸
こっくりした色みのあけび蔓と山ぶどう皮のかごは、青森県にある宮本工芸の工房から。地元弘前市に生まれて、勤続20年の武田太志さんに話をうかがいました。
使い込むほどに鮮やかさを増す、宮本工芸のかご。「品があり、カジュアルなのがかごの魅力」と話す、その言葉の裏には、自然を敬い、素材の美しさを引き出す洗練された手仕事があります。
■編み手はベテランだけでなく新人も
「最盛期は100人ほどの職人がいたと言われていますが、今は10から15人の職人が半月で100か150くらいのかごを制作しています。冬場になるとリンゴ農家との兼業が増え、少し生産のぺースが上がります」

「あけび蔓と山ぶどう皮、素材の質が違うため、それぞれ専門の職人がかごを編んでいます。職人としての年数は一番長い方で50年、短いのは2年くらいの新人もいますね」


■年々、山の環境が変化している
江戸時代、湯治客への土産物からつくり始められた青森の蔓細工。現在は職人の数だけでなく、材料の収穫量も減ってしまっているそう。
「年々、山は荒れていっているように思えてなりません。かつては茅葺屋根の家や大工の木の家が多かったことから山に入って仕事をする人間が多く、そのため山が整備されていました。
山に手が入ると、植物に日光も当たるので、自然の恵みも育ちやすい環境になるんですね」

「ですが、いまは整備されていないジャングルのような状態。
異常気象で雨が多かったり、そうかと思えば水が不足するほど乾燥したり。昔と比べて四季の時期がずれているように感じます。
このような環境が、あけび蔓や山ぶどう皮の減少にも大きく影響してしまっているのです」


■色揃いのよい岩木山のあけび蔓をいかして
収穫量の変化は減少気味だが、年によって色やかたちはそれぞれ。時折、目を見張る美しさに出合うこともあり、そんなできごとが活動の背中を押してくれるそう。
「毎年、本当に違うんです。もう蔓がよい年は無いのかなと思っていたところに『今年はすごい!』と思う年もあり、自然の摂理やパワーに関心させられます」

「同じ青森県でも青森市の蔓は色が不揃いで短く、真っすぐでないものも多い。
弘前市にある岩木山のあけび蔓は色揃いもよくて、長さも三間ほどあり、まっすぐ伸びていてとてもきれいです。
蔓が長いと継ぎ足しも少なくて済み、同じ風合いで大きいかごを編むことができるので仕事がやりやすい」


■使い込むほどに艶が出るように。作業は時間配分が勝負
あけび蔓も山ぶどう皮も、編む以前に両方とも水分調整がとても大事。できるだけ色揃いのよい素材を収穫し、しっかり水を抜くことが美しい風合いをつくります。
「山ぶどう皮は収穫後、1~2週間は天日干し。その後、2~3ヵ月くらい屋内で保管することによって、もとの状態より70%くらい縮みます。
あけび蔓は屋内に半年間干して水分を抜きます。そして節を取り、部位の太さや色をみて、持ち手にしようとか、どこで使うか考えていくのです」

「準備していざ編むのは7日間ほどの作業。3日ほど浸して柔らかくし、4~5日の間に編み上げる。
乾いたものを大きな水槽のような容器に入れ、材料をやわらかくして編んでいきます」

「一度水に浸したら、水が抜けてしまう前に使い切らないとその材料はもう使えません。どれくらいで仕上げられるのか、時間配分が勝負です」

■かごは使うことがいちばんのメンテナンス
「毎日使うと手の脂で艶が出ると言われますが、それは本当です。よく撫でてあげるのも手入れの一つ。とくに山ぶどう皮は明らかに違いが出ます。
ほかにも埃取りに亀の子たわしでこするのもいいですね」

「あけび蔓をたわしでこするときは、かごの外側は編む流れに沿うように。内側は蔓を足している部分があるので目に逆らうようにしてください。
逆にやらないで欲しいのが、保管するときにビニール袋に入れて湿気を集めること。一度水を抜いているため、もう水はいらないのです」

職人や収穫の数が減少していくなか、変わらないのは先人から受け継ぐ知恵や技術。
その灯を絶やさず、二つとない素材そのものの美しさを引き出して、宮本工芸は今日もかごをつくりつづけています。
写真提供:宮本工芸(1~4枚目、7~9枚目)
-

《つくり手ファイル》悲しい日もうれしい日も。人生に役立つものづくり/shuo'
-

《つくり手ファイル》人生に寄り添うジュエリーづくり/cobaco
-

《つくり手ファイル》横振り刺繍が紡ぐ、野の花のジュエリー/鬼塚友紀さん
-

《つくり手ファイル》使う人とのほどよい距離感/JOURNEY草薙亮さん
-

《つくり手ファイル》日本の豚革を活用、未来につながるものづくり/sonor
-

人生に向き合う中で、見つけたセルフケア。「自分の内側が何を望んでいるのか、ひとつずつ向き合う」/fragrance yes 山野辺喜子さん