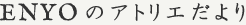フランスルーアンの街で服づくりをするデザイナー、
ソリアノ綾佳さんからのお便りをご紹介します。
ルーアンは、パリから電車で1時間ほどの場所にある街。
この街でソリアノさんは自身の目で選んだリネンで服を仕立て、
年に一度リリース。エンベロープでもその作品をご紹介しています。
ソリアノさんについての紹介記事はこちらから »
2021.10.15
秋めいた、というより朝晩はもう冬の気配がしています。
リネン農家の方が、今月は “lin d’hiver (冬リネン)” の種蒔きをしたと
おしゃっていました。
近年こちらでも収穫時期にあたる夏の猛暑が問題になっており、
栽培時期をずらした農法が始まっているそうです。
本来フラックスは3 〜4 月に種蒔きをしますが、冬リネンはそれを秋に行います。
ノルマンディにはリネンの協同組合があり、その品種研究部門では
冬リネンをはじめ耐病性を持ち繊維が豊富に取れる種子の研究をしています。
興味深いお話を聞けたので、以前見学に訪れたこの協同組合にある加工工場の様子と
ともにレポートしたいと思います。
レッティングを終え畑から回収されたフラックスは、
この工場で茎から繊維を取り出す ”スカッチング” の工程を行います。

▲畑でロール状にまとめたのをこのまま機械に通します
機械で何度も叩いたり梳かしたりを繰り返すと、繊維を覆う表皮や短い繊維が落ちて、
糸を紡ぐ材料になる長い繊維が取れます。

▲銀色の歯がみえますが、櫛で髪を梳かすようにしながら繊維を出します。 落ちた短い繊維も様々な用途に使われ、フラックスに捨てられる部分はありません
マシンが大きな音を立て作業をしているので、それまであたたかいところで
ゴロゴロしていたのに、急に忙しくなっちゃったよ〜!なんて、
そんなことフラックスは言わないでしょうが、畑の景色とまるで異なり圧倒されました。

▲艶々に仕上がりました
そうそう、畑といえば定点観察をしていたのに開花を見逃したことは
前にもお伝えしていましたが、先述の農家さんが大事なことを教えてくれました。
ちゃんと花が咲かないと充分に受粉がされないため、
種をつくることができないのですって。
それは大問題!
今年は悪天候の影響で難しい年だったそうで、例えば強風で茎が倒されても
通常は自力で立ち上がるところ、あまりに雨が続くとそうはいかず、
倒伏したまま収穫前に発酵が始まってしまって……とも話してくれました。
「 リネンづくりはお天道様のご機嫌次第! 」とよくおっしゃるのですが、
こうした状況に置かれても手を加えることはせず、自然に任せるそうです。
散水もしないので本当にお天気が出来を左右しています。
しかし、今年のように難しい年の繊維で織った生地はいまいちなんじゃ……
といった心配はご無用。
収穫年、品種、耕作した畑等をきちんと分類してストックしておき、
様々なフラックスを混ぜて平均化するため、いつでも品質を安定させることが
できるからです。
的確にミックスをする技術も求められますね。
フランス国内にはリネンの紡績工場がほとんどないので、
種から生まれた長繊維の多くは国境を越えます。

▲大半は中国に輸出され紡績されます
自分が手にする物がどこからどんなふうにやってきたか、
それは勿論リネンだけではなくて全てにいえることですが、
その旅路を想像すると無下にはできません。
ENYO ソリアノ
http://laviedenyo.blogspot.com/