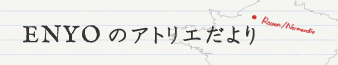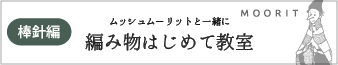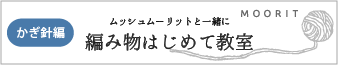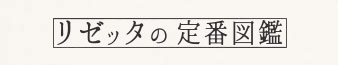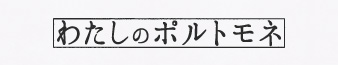イベント・ニュースや読みもの note
2018.11.29

《つくり手ファイル》水の気配、静寂な空気をまとう焼きもの/陶磁器作家塚崎愛さん
「夜の水たまりって白い色をしているんですよ」そう教えてくれたのは、陶磁器作家の塚崎愛さん。土でありながら感じさせる瑞々しさと、静けさを帯びた焼き物を手掛ける塚崎さんを訪ねて、横浜市郊外のアトリエにお邪魔しました。

■月時雨と糸雨のジュエリーベース
白い土でつくられた丸いジュエリーベースは、塚崎さんのデビュー作です。
「瑞々しさ」という言葉がぴったりなその作品を使う時、水面にそっと花びらを浮かべるような、そんな感覚に陥ります。


▲つやつやとした釉薬がかかったジュエリーベース。触れると波紋が広がりそう
ジュエリーベースはつくろうと思って生まれたものではなく、偶然の出来事から誕生したもの。それはまさに収穫でした。
「釉薬の色を見たくて、マグカップに注いで焼いてみたんです。窯を開けてみると、釉薬を境にカップが上下に割れていて…収縮率の違いで割れてしまったんでしょうね。でも、それがとてもきれいだったんです」
そこからブラッシュアップさせて、青と白2色のジュエリーベースが完成しました。それぞれ「雨」にちなんだ名前がつけられています。

写真提供:megumi tsukazaki
「白い方は月夜に降る雨を思わせたので、月時雨(つきしぐれ)と名付けました。夜の水たまりって、よく見ると白いんですよ。
貫入や気泡が入った青色の方は、ぴちぴちと音を立ててはじける細い雨のようだったので、糸雨(いとさめ)という名にしました」

▲陶磁器作家の塚崎愛さん。陶芸との出合いは大学の授業で。その後製菓店勤務などを経て、陶芸学校に入学し基礎から学びます

▲成型を終えた作品の数々。型は使わずに、ろくろでつくります
■土で感じさせる「水」
作品の名前は、つくり終えてから決めます。水に関する言葉がすっと出てくるのは、日ごろから意識して水を見ているから。
「陶芸学校で”表現すること”が課題として出たのですが、何を表現すればよいかわからなくてじっくりと自分に聞いてみたんです。そうしたら”水たまり”や”お風呂の蓋の裏側についた水滴”など身の回りにある水に興味を持って見ていたことを思い出して、”水”というテーマにたどり着きました」
不思議なもので、土でつくられたものなのに水を感じさせる塚崎さんの作品。そんな話を聞いて、理由がわかった気がしました。

ジュエリーベースにつづいて完成したのが、一輪挿し「水になりゆく 花うつわ」。ポタポタとしずくがたまったような底の部分がまずイメージにあり、そこから上へ上へとつくっていった作品です。

▲2番目の作品となる一輪挿し。粗削りな感じの側面が、底面のプルンとした潤いを際立たせます
■温かみがありながら、素朴になりすぎず

塚崎さんは、陶器に使う土と磁器に使う土を調合してつくります。洋食器に象徴されるきりりとした空気と、土ならではの温かみ。どの作品もその両方を兼ね備えています。

素材の個性を生かすために決めているのが、主題を絞ること。
例えば釉薬。細かく貫入が入る艶のあるものと、ランダムに貫入が入って動きが出るマットなものを使っているのですが、作品に合わせて使い分けています。
「主張は1個って決めているんです。“かたち”も“質感”もではなくて、シンプルなかたちにはマットな釉薬を、特徴のあるかたちには艶のある釉薬を選んでいます」
ちなみに旅行でも行先は1か所と決めている塚崎さん。あれもこれも欲張らない潔さが、作品にもあらわれています。

▲窯の中で焼きあがったフラワーベース。「素朴な土っぽさから印象が変わり、蓋を開ける時に収穫感があるんです。自分がつくったものなのに、現れたって感じがします」
■飾るものと、使うものと

▲手でかたちづくられた耳飾り
その後ラインナップには、アクセサリーと器が加わりました。
アクセサリーは、歴史を積み重ねた化石のような作品や、丹念に磨き上げた宝石のような作品など表情が多彩。人の手でつくられたものなのに、自然のもののような美しさです。


▲アクセサリーは桐箱に入れて、塚崎さん自身が一つ一つオイルを塗っています
細かい貫入が入った器は、なんとコーヒーで染めたもの。真っ白な器の上を走る茶色の線が味わい深くて、ずっと見ていても飽きさせません。
「主役は貫入だから、かたちではなく貫入に目がいくようにつくっています」と塚崎さん。器もやっぱり、主張は1個です。

▲コーヒーで染めたプレート(右)。貫入の入り方がどれも異なり、見とれてしまいます

▲塚崎さんの器でお茶をいただきました。テーブルクロスもコーヒーで染めたもの
飾るもの、身に着けるもの、食卓で使うものと、用途は様々ですが使う土も釉薬も同じ。そして、そこには一本の筋が通った美しさのルールがあります。

megumi tsukazaki ~静寂の白~
塚崎さんの展示会を二子玉川のリネンバードホームとエンベロープオンラインショップで開催します。期間中には、塚崎さんによるワークショップも開催。白い陶器のピアス・イヤリングとアクセサリーBOXをつくります。
リネンバードホーム:2018年12月13日(木)~25日(火)
エンベロープオンラインショップ:2018年12月13日(木)12時~25日(火)15時